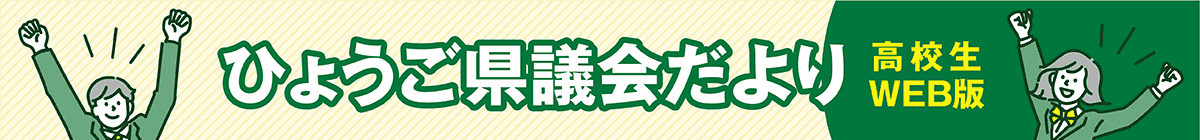サイト内検索
兵庫県議会トップページ > 県議会の概要 > 議会広報 > ひょうご県議会だより高校生WEB版 > 取材記事 > 【直接インタビュー】ほんまに私達のこと知ってんの??
ここから本文です。
更新日:2025年3月11日

【直接インタビュー】ほんまに私達のこと知ってんの??
夙川高等学校/政界探検ガールズ
取材記事
「若者のための政策」とか言うけどほんまに私達のこと知ってんの??議員さんに直接インタビューしてみた!
若者のこと意外と考えてくれているのかも ~プロローグ~
神戸市では高校生の通学定期が無償化され、議会への興味が芽生えた時期。ふと兵庫県議会はどんなことを取り決めているのか興味が湧き、このプロジェクト「ひょうご県議会だより高校生WEB版」に参加しました。
初めて兵庫県議会を訪問した際、地方議会協議会の「若者・Z世代が輝く兵庫づくりと主権者教育」という議題の議会を見学しました。そこでは若者に国や社会の問題を自分事として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく力をつけてもらうためには中高生が政治に触れる機会を作ることが必要だという話をしていました。そもそも私達は、若者の投票率は低く若者のための政策は票には繋がらない、私達高校生は選挙権を持っていないから政治に参加したいと考えてもできない。だからこそ高齢者への福祉ばかりが考えられているのだと思っていたので、若者についての議会があることにまず驚きました。その議会の中で私達が感じたのは
「若者のこと、意外に気にかけてくれているかも」
「もしかしたら自分達の方も見てくれているのかも・・・」
ということ。
「自分達が動けば変わるという経験が大事」
議会に参加していた一人の議員さんの声で気づきました。「私達は諦めていたのかもしれない」と。
どうせ声を上げても世の中何も変わらないと、そう思い込んでいました。でも本当は、自分達ができないだろうと考えていたことも議員さんは考えてくれているかもしれない。そう感じました。
ホンマに若者のこと知ってんの??
ただ、兵庫県議会では「若者のために」とか「若者が輝く」とか言っているけど、「実際若者のことホンマに知っているのか」という疑問が浮かんできました。そこで今回は学校内の私達と同じ高校2年生に「困っているけど諦めていたこと」について自由記述形式のアンケート調査を行いました。その中で出てきた、通学で使用する「自転車」の利用法と自分たちが自由に勉強するスペースである「自習室」にフォーカスをあて、せっかくなら取材者たちの地域に関わりが深い議員さんとお話がしたいと思い、前田ともき議員と石井秀武議員と対談しました。
「ホンマに若者のこと知ってんの??」ということを確認したいため、2つの質問はクイズ形式で質問することに決め、対談に臨みました。



「私たち、ちゃんと歩み寄っていたかな?」 対談その1:前田ともき議員
東灘区選出の前田議員。取材者工藤が中学受験をしていなければこの方と同じ中学に通うことになっていたとても親しみを感じる議員です。
本題の前に、若者の投票率について質問しました。
Q1.実際、投票率が低い若者のことについてどう思っていますか?
前田議員:困りごととか社会に対する想いっていうのをなるべくいろんな方の意見を聞きながら政策に反映していきたいので、こういう機会だとか僕らが街頭演説をしている時に問題点をぶつけてくれるとありがたいですね。投票しないといけないとか二元代表制がどうとか学ぶよりも、実際に自分の高校生活で感じている問題点をどういうプロセスを経て改善していくのかっていうところを議論したほうが多分、主権者教育にも繋がっていくと思うんですよね。
ーここで私達が議会に参加して気がついた「自分達の声で政治が変わる実感の重要性」を確認できました。そして、本題である「高校生の自転車事情」について質問をしました。

Q2.私達高校生はとある乗り物の利用法で悩んでいます。その乗り物とは何でしょうか?
1.Loop 2.自転車 3.バス
前田議員:自転車の乗り方わからへんとかじゃないっすよね(笑)。バスで料金高いとか?ちゃうか。Loopが校則で禁止されているとか?
ー私達が持ってきた理由とは異なりながらも正解の自転車を選択されました。2024年度からヘルメットが努力義務になり、新しい交通ルールが紙で配られたものの、いまいちよくわからなくて困っていて、交通ルールを教えてくれる教室のようなものを開催してほしいという声があったことを説明しました。
前田議員:確かに改めて考えると右折する時に二段階右折しないといけないとか細かい話を考えるとね、いろいろな疑問が残りますもんね。特に免許を取っている人からすると道路標識とか勉強するけど、高校生とか校則で免許取得禁止のところもあるし、そういうのを習わないですもんね。いきなり車両扱いで厳格化されても困るよねって話ですよね。
ー交通ルール以外にも、坂の多い神戸の街で住宅地が入り組んでいて細い道が結構あり、自転車だから道路を走れと言われるけど、道路を走ると車とすれすれになって怖いという声があること、以前に学校の海外研修旅行でイギリス、フランス、ドイツ、オーストリアに行ったときに、土地が広いということもあるけど自転車専用道路があり、自転車が安心して運転できる場所が日本にもあるといいなと思ったけど、「どこに言えばいいか分からない」という悩みを相談しました。
前田議員:それは警察と県道を所管しているところがやるんですけど、自転車を車道で走らせると危ないので、車道の一部をブルーのラインでひいて、車が走る専用道路と自転車専用道路にしていこうっていう流れはありますね。道路に幅がある程度あればできるんですけど、そうじゃないところをどうしていくかっていうのが非常に難しいところではあるんですけどね。歩道の上を走ると自転車は強者になりますが、車道を走ると弱者になりますからね。あとは予算の問題。何千キロも道路はあるので、設置のコストとかそもそも設置できる面積があるのかどうかも含めて優先順位をつけながらやっていかざるを得ないというのが正直なところですね。
ー学校での友達間の話でも予算はどうなのかなっていう話題が出て、「きっと予算がないんだろうな」という予想はできても、実際どうなのかを知る手段がなく、公式LINEのような兵庫県と直接やり取りできる制度があったらいいなと思っていることを伝え、実際そのような動きがあるのかを聞いてみました。
Q3.公式LINEのような兵庫県と直接やり取りをする制度が作られる動きはないのですか?
前田議員:兵庫県はまだそういうのはなかったかな。ただ、知る手段で言えば県議会の議事録で興味あるワードを検索したら、それに関した質疑とか経緯とかが結構出てきたりするのでわかりやすいと思います。例えばね、道路の停止線の白線って兵庫県の場合かすれていてもメンテナンスをするコストがなくて、そのままだったりするんですよ。数百キロベースで結構やっているんですけど、その中でも自転車のことを考えると、どのエリアが一番危険性が高いか等、その中の優先順位も全部載っています。みんなの意見を見て、なんですぐに対応ができへんのかなって。そういう裏側の事情もあってやりたくてもやれない、優先順位があって前後しちゃうっていうところもあるので、じれったいなって僕自身も思うことがあるのですけどね。
ーこの話を聞いて、ふと感じた「そういう裏側の事情とかを直接話せるような機会がいっぱいあればいい」という思いをつぶやきました。
前田議員:そうですよね。例えば県立高校生の生徒会長がみんな集まって高校生県議会で直接話す機会があっていいと思うし、ほとんどの議員や政治家はそういう皆さんの意見をちゃんと真摯に聞きたいという思いは常に持っているはずですけどね。

ー 最後に一番私たちが聞きたかったことを ー
Q4.どうせ無理と思って諦めていたことを諦めないようにするにはどうすればいいですか?
前田議員:一つは小さな成功体験。自分達の一つの意見が議会なり役所なりに問題提起をしたとき、それが実際改善されたなという成功体験をどれだけ積み重ねられるかなっていう点と、役所も議会もいろんな学生生活をより良くするために色んな話をしているんだよっていうのを議事録で検索するのが大事かなと思うんですよね。最近あったのが、朝早くの満員電車での痴漢対策とか給食を自校調理で温かいものにした方がいいんじゃないかとか、部活動のあり方とかね。
ー若者の投票率が低いままで若者のための政策などしておらず、自分の票につながる高齢者の方々のための支援ばっかりしているのかと思っていたことを伝えると・・・。
前田議員:少なくとも僕自身は投票権がないからとか、例えば僕は東灘区ですけど東灘区民のためにっていう発想は全くなくて、兵庫県全体がというより、日本全体が最適で納得感のある税金の使い道をされているかっていう観点で議論するので、仮に投票権がなくても選挙区民じゃなくても、これ面白いねっていう意見があれば積極的に取り入れますしね。神戸市会議員でもいいし、県議会議員でもいいし、神戸市の所管であれそれは関係なく、兵庫県議会の人が多分処理するし、言いやすそうな人とか面白そうな人とかに投げていいと思いますね。予算の問題もあるし、すぐ変わるかって言ったらなかなか難しいところもあるんですけどね。
ー歩み寄るということ。自分達も意見や文句を言うばかりじゃなくて、議事録を見たりして、できない事情をちゃんと知るとか、話を聞く姿勢もあるんだと理解する歩み寄りが大事だなと気づいた対談でした。

「逆に若者が壁を作っているかも?!」 対談その2:石井秀武議員
西区選出の石井議員。取材者伊東の最寄り駅でよく朝に挨拶活動をしていて馴染み深い議員です。石井議員には自習室についての質問を聞いてみました。
Q1.私達高校生は兵庫県に“ある場所”が少なくて困っています。その場所とは何でしょうか?
1.SNS映えスポット 2.トレーニングルーム 3.自習室
石井議員:どれやろな。どれも少ないかもわからへんけど、トレーニングルームが欲しい言う人はやっぱりそれに興味あるやろうしね。案外自習室ちゃうかな。
ー迷った末、正解の自習室を選択。自習できる場所が少なく、例えば西神南にある西図書館は二時間で席を譲らないといけないルールがあり、連続で予約が必要なこと、またそもそも勉強できる場所自体が少ないことをお伝えしました。
石井議員:石川県立図書館というのが新しく出来てそれを見に行かしてもらったんだけど、自習室というかそういう勉強できるスペースが図書館の色んなところにあって、これは兵庫県でもできればいいなってちょうど思ったところやね。
ー実際に若者のために自習できるスペースを考えてくれていることが分かりました。

Q2.公式LINEのような兵庫県議員さんに直接伝えることのできるチャットやアプリを作るのはどうですか?
石井議員:できないことはないんやけどね。ただシステムをどういう風に作っていくかということだけで。学校の環境のこととか自習室のこととか、それこそSNS映えスポットのこととかいろんな分野ごとにまた変わっていくからテーマ分けしないといけないからね。
ー問題提起はされながらも制度自体には肯定的な意見が!今まで議員さんはみんなすごくお堅い人だと思っていた分、肯定的な意見が返ってきてとても嬉しかったです。

Q3.県民が一方的な要望を言うだけとなると大変になりませんか?
石井議員:そういう要望を聞くことは大事やからね。私らも今の若い子がどういうことを望んで考えているのかはさっぱり分からないから、困っていたり、悩んでいたり、そういうのを文面を通して知るのも大事なことだと思うんでね。それを政策に持って行くのはもうちょっと熱量がいるかもだけど。若者の要望も、私ら投票権を持っている人だけを対象にしているわけじゃないからたくさん知りたいし。いずれまた投票権を持つわけやし、そういう意味では一番大事な存在やから。
Q4.若者の投票率が低いことに関して実際どう思っていますか?
石井議員:投票に行かへんのは自分らにやっぱり関心がないってことやから、それは私らに責任があるんかな。でも朝、挨拶活動をするときは通学で駅を使う若い子達にも必ず声をかけるようにしていて、そういうことによって親しみを持ってもらうのが一番大事なことだし、その子達が政治に関心を持ってもらうのが一番やと思うしね。その子らがいずれ有権者にもなっていくわけやし。急に挨拶されてもね、若者のお父さんお母さんより年上だからちょっと怖いのもあるかもしれんけど、一般的に議員している人はもっとフランクに話しかけていっても返事はしてくれると思うし。逆に皆さんが壁を作っているかもしれない。だからこういう機会に高校生を中心に私らも議会でこういうことをやっているよというのをアピールしながら、その議会で皆さんの学校の環境とか学習環境とかを改善していくような形でしっかり取り組んでいるっていう姿が見えてきたら、もっと政治に関心を持って投票率もあがっていくやろうし。お互いが壁を作らんといけたらいいよね。
ー怖いと思っている、壁を作っているかもしれない。今までの議員さんのイメージと合致していて納得しました。最後に伊東との近所の話題が盛り上がり、4時前に起きていることや、月に何度かは1時間かけて自宅近くの高塚山へ散歩していること、お正月には高塚山へご来光を見に行っている話を聞いて、親近感が湧き、この対談が終わる時にはもう議員さんはお堅くて怖いというイメージはなくなりました。

互いに歩み寄る姿勢を大切にする ~編集後記~
地方議会協議会を見学した時に感じた「若者のこと、意外に気にかけてくれているかも」という思い。それは間違っていませんでした。たくさんの議員さんが思ったより若者のことを考えて議論してくれていることがわかりました。正直、見学するまでは議会は形式張った厳かな場所、議員さんはお堅くて怖いと思い込んでいたので、対談の中で若い世代が壁を作っている可能性もあるのではないかと言われてとてもドキッとしました。今回実際に議会を見学して和やかに笑っている議員さんたちを見て、そしてとてもやさしい言葉遣いで真摯に質問に答えてくださる前田議員や、冗談や近所の話で盛り上がった石井議員との対談を通して怖いというイメージは全くなくなりました。
確かに私達高校生には選挙に参加することはできないし、どう頑張っても若者の投票率を高くすることはできません。けれど、それは選挙に参加できないだけのことであって、政治に参加できないわけではない。これも今回のプロジェクトを通して学んだ大きなことの一つです。もし困ったことがあれば、もしこうしてほしいってことがあれば、議員さんに話せば真剣に考えてもらえる。その分、何でもかんでも話すのではなく議事録を読んで県議会がやっていることを知ろうとする努力を欠かさないで、互いに歩み寄る姿勢を大事にしていきたいと思いました。
お問い合わせ