ここから本文です。
緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)
緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)は、緑を軸とし、広域的な見地から土地利用を考えながら、自然に配慮した開発を誘導することにより、自然と調和した地域環境の形成を図ろうとする条例です。
緑条例 緑地面積の算定等に係る運用について
中高木による緑化を誘導するため、緑地面積の算定方法等に関する運用を見直しました。
(令和6年4月1日以降に届出又は協議をするものに適用)
緑条例 緑地面積の算定等に係る運用 概要(PDF:131KB)
緑条例の目的
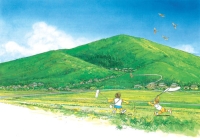 緑豊かな環境形成地域のイメージ |
緑条例は、都市計画法により市街化区域と市街化調整区域とに区分された線引き都市計画区域以外の地域において、適切な土地利用の推進、森林・緑地の保全、緑化の推進、優れた景観の形成の観点から開発行為を適正に誘導することにより、緑豊かな地域環境の形成を図ろうとするものです。
緑条例のしくみ
- 1.緑豊かな環境形成地域の指定
自然環境や社会的なまとまりから広域的に緑豊かな地域環境の形成を図ろうとする地域を緑豊かな環境形成地域として指定し、条例を適用しています。- 現在、8つの地域(北播磨北部、北播磨南部、中播磨、西播磨、南但馬、北但馬、丹波、淡路)を指定しています。
- 2.地域環境形成基本方針の決定
緑豊かな環境形成地域における土地利用の方向、景観形成、住民主体のまちづくりなど地域環境形成に関する基本的な方向を、地域環境形成基本方針として定めています。 - 3.環境形成区域の指定
緑豊かな環境形成地域を、5種の環境形成地域(第1号区域、第2号区域、第3号区域、第4号区域、第2項区域)に区分しています。
|
環境形成区域 |
区域の設定 |
|---|---|
|
第1号区域 (森を守る区域) |
森林など特に緑豊かな地域環境の保全を図るべき区域 |
|
第2号区域 (森を生かす区域) |
森林と建築物や公共施設が調和した緑豊かな地域環境の形成を図るべき区域 |
|
第3号区域 (さとの区域) |
農地と建築物や公共施設が調和した緑豊かな地域環境の形成を図るべき区域 |
|
第4号区域 (まちの区域) |
市街地又は相当規模の集落として緑豊かな地域環境の形成を図るべき区域 |
|
第2項区域 |
その他、地域の特性、地域整備の方針などからみて上記以外に定める区域 |
( )内の名称は緑豊かな環境形成地域によって異なります
- 4.地域環境形成基準等の決定
環境形成区域ごとに開発行為に係る森林の保全、緑化修景等の地域環境形成基準(第1号地域は許可基準)を定めます。 - 5.開発行為等の誘導
一定規模以上の開発行為等について、協議・協定、届出等の手続を求め、地域環境形成基準等をもとに適正に誘導します。
緑条例の施行地域(緑豊かな環境形成地域)
兵庫県では、平成7年3月から丹波及び淡路地域において緑条例を施行してきましたが、平成15年度から緑条例を全県的に適用拡大する取組みを開始し、平成17年11月から北播磨北部、中播磨、西播磨及び南但馬地域において、平成18年11月から北播磨南部及び北但馬地域において施行しました。
対象となる開発行為
緑条例の施行地域では、1,000平方メートル以上(一部の区域は500平方メートル以上)の規模の開発行為を行おうとする場合は、市町や県との協議・協定、届出等の手続が必要です。ただし、自己用住宅の新築・増改築や通常の管理行為、軽易な行為などは、対象外です。
開発工事に際しては、環境形成区域ごとに定められた緑化修景等の基準をもとに、開発地の森林の保全や建物の周辺の緑化などが必要となります。
|
環境形成区域 |
手続 |
手続が必要な開発面積 |
|---|---|---|
|
第1号区域 (森を守る区域) |
許可 |
500平方メートル以上 |
|
第2号区域 (森を生かす区域) |
協議・協定 |
1,000平方メートル以上 (丹波地域は500平方メートル以上) |
|
第3号区域 (さとの区域) |
協議・協定 |
|
|
第4号区域 (まちの区域) |
届出 |
|
|
第2項区域 |
協議・協定 |
- 問い合わせ先
問い合わせ先一覧(PDF:37KB)- 地域や開発行為の規模により問い合わせ先が異なりますので、注意してください。
- 各地域の運用
- 緑条例の運用(北播磨北部地域)
- 緑条例の運用(北播磨南部地域)
- 緑条例の運用(中播磨地域)
- 緑条例の運用(西播磨地域)※姫路市は中播磨地域に含まれますが、旧安富町の区域のみ西播磨地域に含まれます。
- 緑条例の運用(南但馬地域)
- 緑条例の運用(北但馬地域)
- 緑条例の運用(丹波地域)
- 緑条例の運用(淡路地域)
住民主体のまちづくり(計画整備地区制度)
 住民主体のまちづくり |
緑条例には、住民が主体となって、自分たちで自分たちの地区のルールづくりを行う制度(計画整備地区制度)があります。
集落などの一定のまとまりのある地区において、住民の方々が話し合い、自分たちのまちのルール(地区整備計画)を決めることができる制度です。
- 地区整備計画の内容は
住民の方々が話し合い、地区の将来像を描き、将来に望ましい土地利用計画、緑化計画、景観計画、建築計画などを定めることができます。県や市町では、アドバイザー派遣など計画策定についての支援を行っていますので、ご相談ください。 - 地区整備計画が認定されると
認定計画に係る区域(計画整備地区)内においては、すべての開発行為、建築行為について市町への届出が必要になるとともに、緑条例が適用される一般の地域における基準より地区整備計画による基準が優先される仕組みになっています。 - 現在の計画整備地区(一覧表は下の関連資料「整備計画認定実績」をご覧下さい。)
- 【西播磨地域】
安志北の台地区整備計画(姫路市安富町※)(PDF:4,231KB)
※姫路市は中播磨地域に含まれますが、旧安富町の区域のみ西播磨地域に含まれます。 - 【南但馬地域】
八鹿町岩崎区整備計画(養父市)(PDF:4,526KB)
城下町八木地区整備計画(養父市)(PDF:1,662KB) - 【丹波地域】
丹南町野中地区整備計画(丹波篠山市)(PDF:1,051KB)
氷上町石生駅西周辺地区整備計画(丹波市)(PDF:1,148KB)
篠山市日置地区整備計画(丹波篠山市)(PDF:903KB)
篠山市乗竹地区整備計画(丹波篠山市)(PDF:918KB)
篠山市黒田地区整備計画(丹波篠山市)(PDF:787KB)
篠山市野間地区整備計画(丹波篠山市)(PDF:424KB)
丹波市国領区整備計画(丹波市)(PDF:911KB)
丹波市多田区整備計画(丹波市)(PDF:7,307KB)
篠山市味間奥地区整備計画(丹波篠山市)(PDF:1,795KB)
篠山市国道176号沿道地区整備計画(丹波篠山市)(PDF:582KB)
篠山市東岡屋地区整備計画(丹波篠山市)(PDF:832KB)
篠山市城下町北地区整備計画(丹波篠山市)(PDF:574KB)
篠山市丹南篠山口インターチェンジ周辺地区整備計画(丹波篠山市)(PDF:1,232KB)
丹波篠山市上立杭地区整備計画(丹波篠山市)(PDF:1,741KB)
丹波篠山市宇土地区整備計画(丹波篠山市)(PDF:550KB) - 【淡路地域】
洲本市新都心地区整備計画(洲本市)(PDF:5,833KB)
- 【西播磨地域】
- 今後、整備計画の認定に向けて地域が取り組んでいる広域沿道土地利用計画(緑条例に基づく手続きは求めていませんが、地域と協議しながら開発行為等を進めていただくこととなります。)
- 【中播磨地域・南但馬地域】
国道312号広域沿道土地利用計画(朝来市、神河町)(PDF:5,598KB) - 【南但馬地域】
国道9号広域沿道土地利用計画(養父市)(PDF:2,554KB) - 【丹波地域】
丹波地域広域沿道土地利用計画(国道176号)(丹波市※)(PDF:5,509KB)
※本計画のうち、丹波篠山市の区域については、「篠山市国道176号沿道地区整備計画」として知事の認定を受けていますので、こちら(PDF:582KB)をご覧ください。
- 【中播磨地域・南但馬地域】
関連メニュー
お問い合わせ
