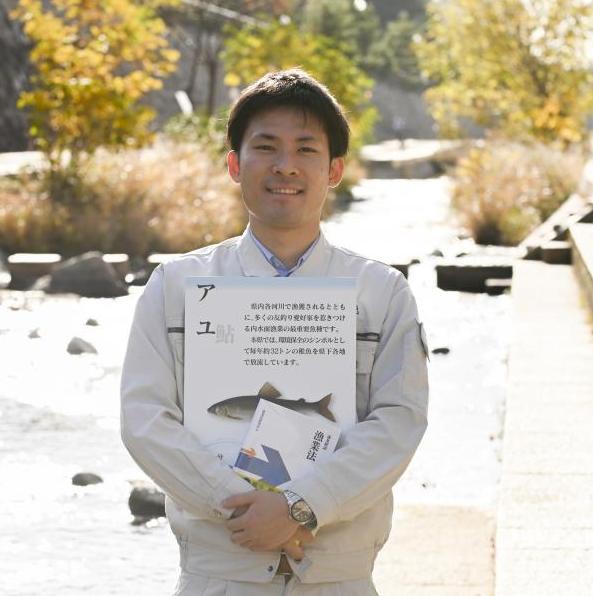ここから本文です。
水産職
見ることも食べることも大好きな魚。
「魚が獲れる海」を目標に、地元兵庫県の水産業を活気づけたい。
|
農林水産部 水産漁港課 副主任 |
Q.なぜ民間ではなく公務員を目指したのか、またなぜ各市町村ではなく県を目指したのか?
幼い頃から魚が大好きで、中学生の時に漁協で職業体験をさせていただいた際に、「最近は魚が獲れない」という漁業者の本音を聞き、将来は地元兵庫県の漁業者の力になりたいと思ったことがきっかけです。兵庫県は日本の縮図とも言われ、北は日本海、南は瀬戸内海から紀伊水道を経て太平洋に続く3つの海に面しており、この特色ある兵庫県で、水産に携わる仕事がしたいと思い県職員を志望しました。
Q.これまでの業務で大変だったこと・嬉しかったことは?
令和4年11月に兵庫県明石市で第41回全国豊かな海づくり大会~御食国ひょうご~が開催されました。私はこの大会の準備室の一員として、関係者と大会直前まで何度も打合せを行ったほか、リハーサルや大会の運営スタッフへの説明会など入念に準備を進めてきました。コロナ禍の影響もあり3年に渡って準備してきた大会だったので、大会直前は不安で寝れないこともありましたが、無事に開催を迎えることができ、本県が目指す豊かな海の創出に向けた取組を積極的に発信することができたと自負しています。
Q.現在の仕事をする上で心がけていること・大事にしていることは?
現在の主な業務は、内水面漁業の振興や漁業調整事務です。兵庫県の内水面漁業は、アユをはじめとする河川漁業やウナギ等の養殖業など多岐に渡りますが、近年、河川漁業・養殖業ともに生産量や生産金額が減少傾向にあるほか、外来魚やカワウ等の被害が深刻化しています。この状況になんとか歯止めをかけるため、まずは現場の意見に耳を傾け、「今」の状況を知ることが大切だと考えています。また内水面漁業は水産物の供給だけでなく、釣りなどを通じた自然と親しむ場の提供など、県民生活の豊かさを創出する様々な役割を担っているほか、河川の栄養は海に流れ、豊かな海づくりにも寄与しています。このことから、引き続き内水面漁業の振興に努めるとともに、多面的機能の重要性もPRしていきたいと考えています。
Q.県職員の仕事のどういったところに難しさを感じるか?また、県職員として働く魅力やおもしろさはどのようなときに感じるか?
兵庫県では海域の特性に応じた様々な漁業が営まれています。日本海では沖合底びき網漁業などの沖合漁業を主体に、ズワイガニ、カレイ類などを、瀬戸内海では船びき網漁業や小型底びき網漁業などを主体に、シラス、イカナゴ、マダコなどを水揚げし、ノリをはじめとした養殖業も盛んです。一方で、河川や湖沼ではアユなどを対象とした内水面漁業が営まれており、こんなに魅力ある水産県は他にはないと考えています。これまで、現場で漁業者と一緒に取り組んだ魚食普及活動や、船上からの受精卵放流など、様々な活動に携わらせていただきましたが、私自身、魚を見ること、食べることも大好きなので、これからも兵庫県の水産業が元気で活気づくよう尽力したいです。
Q.今後チャレンジしたいことやいつかやってみたいことは?
現在の業務は県内の漁業調整事務を中心に、水産庁などの中央省庁や、他府県の漁業者との会議などに出席しています。会議では、活発な意見交換が行われるほか、各府県で取り組む優良事例の紹介や、各々が抱える課題などを情報共有しています。私自身、今年度からの担当業務なので、まだまだ知識不足な点もありますが、今後は様々な機会から積極的に情報を収集し、本県の水産業振興に役立てたいです。
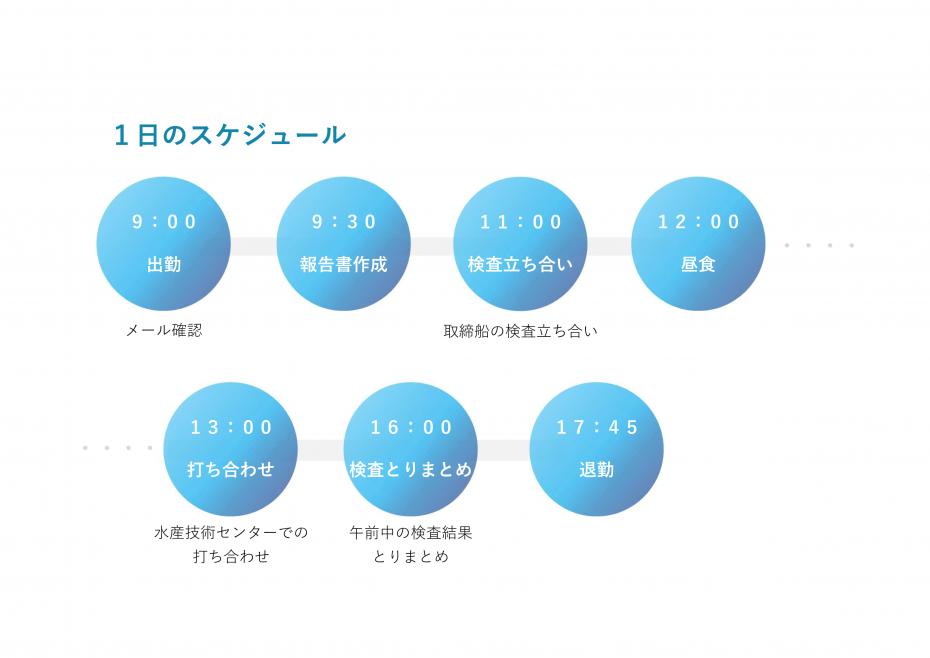 これまでの配属先
これまでの配属先
平成30年4月 洲本農林水産振興事務所 水産課
令和2年4月 農林水産部 全国豊かな海づくり大会推進室 全国豊かな海づくり大会企画課
令和5年4月 現所属
魚への情熱と、大学で学んだ環境保全の知識。地元のために活かしたい。
|
農林水産部 流通戦略課 副主任 |
Q.姫路農林水産振興事務所での仕事内容は?
環境保全や魚食普及、漁業者の経営支援などを担当しています。環境保全については、海底を耕して海底環境を改善する「海底耕うん事業」の事務や、人工増殖場の効果調査を担当しており、魚食普及については、漁業協同組合が主体となって行う販売促進活動等の支援をしています。また、漁業者の経営支援として、漁船や漁船のエンジンの導入支援等も担当しており、水産業をいろいろな面からサポートしています。
Q.兵庫県職員を目指したきっかけは?
実家が海の近くということもあり、昔から魚の飼育や観察、料理が好きでしたが、高校生の頃、全国的に水産物の消費量が減っている上に、資源としての魚の量も減っていることを知り、水産業に携わる仕事がしたいと思いました。水産系の大学に進学し、海洋生物の生態を研究テーマとしながら、環境保全について勉強したので、その知識を活かして地元である兵庫県で水産業の振興がしたいと考え、水産職を志望しました。
Q.仕事の魅力ややりがいは?
県職員として水産業に関わっていると、漁協や水産関係の方はもちろん、環境生物調査や土木関係の会社の方など、様々な業種の方と意見を交わす機会が多く、自分の視野を広げていけるのがこの仕事の魅力です。いろいろな考え方を聞き、それぞれの視点に立った考え方ができるようになるので、県全体の水産業振興を考え、幅広くサポートしていくために役立つ経験を得ることができます。
Q.これからの目標は?
「牡蠣」といえば、広島県のイメージがありますが、兵庫県でも生産量は多く、約40年前から播磨地域で養殖が始まった頃は知名度が低く、広く知ってもらうことが課題でした。そこから、公共交通機関にポスターやチラシを掲示してもらったり、新聞にチラシを折り込んだり、レシピ本を作ったり、かき祭りのようなイベントを開催するなど、「播磨のかき」として漁協等と県が協力して地道にPRを続けてきました。その結果、県内各地はもちろん、県外からもたくさんの方が食べに来てくださるようになりました。これらの取組は、地域の強みを活かした成功例の一つだと思います。私も、地域の漁業を底上げできるような水産振興を目指しています。
これまでの配属先
平成31年4月 農政環境部 農林水産局 水産課
令和3年4月 姫路農林水産振興事務所 水産課
令和6年4月 現所属
関連メニュー
お問い合わせ